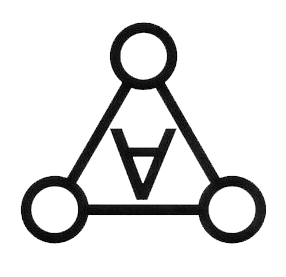つい先日まで故郷の余市へ帰省していた。
夏の帰省で余市個展の前日に母が骨折して手術となり、2ヶ月半もの間入院していたが11月8日に退院が決定し、また以前のように一人で暮らせるようになるためにしばらくの間、一緒に過ごすためだった。しかし、退院した日からとても痛そうな顔をしていて、顔色も悪く、声も低く小さい。まずはお風呂に入れてあげようと余市市内に暮らす妹と2人で服を脱がせてみると、手術した左肩の縫い目の周囲が赤く、その中心が紫色になっていた。妹もその全体像を初めて見たといい、とても驚いていた。なんでも10月10日頃に面会へ行った時に看護士の方から左の脇の下が少し赤くなっていると聞かされ、寝間着で刷れたのでしょうかねぇと言っていたという。が、それから1ヶ月の間にこんなに広がっていたのかと……。それからの毎日を母とともに過ごす中で、あまりにも痛みを訴え続ける母の様子を見ていて「何かおかしいのでは?」と思うようになった。私自身も骨折を経験している身として、手術からもう2ヶ月半も経っているというのに、こんなに痛み続けるものなのだろうか?という思いが浮かんできたのだ。「痛い痛い」と言い続ける母を傍らに、ただひたすらにクリーニングをし続けていたのだが、昼間だけでなく夜の寝ている間にも聞こえてくる母の悲痛な声に「やっぱり、絶対におかしい」と確信した。
私に思い浮かんだのは、ファンの方で東京で整形外科医として開業されている方のこと。「彼にメールをしてみよう」と早速母の状態を送ってみた。突然のメールにもかかわらず、すぐに返信がきて「患部の写真を送ってください」とのこと。事情を説明し、痛がる母の上半身を脱がせ写真を撮り送った。するとすぐに「感染症により局部に膿溜まりができていると思われます。緊急で診てもらうように」とのことだった。妹によると次回の検診は12月5日となっているとのこと。「そんなに先では駄目です。とにかく早急に」と言われ、すぐに妹が電話をしてくれて検査を受けることになり、血液検査ではわからなかったが、造影剤を使用したCT検査により、内部に入れた金属周辺に膿が溜まって感染症を起こしていると判明、即手術が必要となり、再び入院となったのだった。退院してから、わずか9日目のことだった…。妹と一緒に入院に付き添いながら、退院祝いの喜びの気持ちで、胸を躍らせながら訪れた9日前を思い出し複雑な心境だった。その再入院が11月17日。翌18日が手術だったが、私はこの日に帰らなければならなかった。「手術には付き添えないし、無事終わったら私に電話が来ることになっているから、そしたらすぐ、お姉ちゃんに連絡するからね」と妹。その日は祈り続けながら山梨へと向かった。手術は16時開始となり、丁度その時間は飛行機の中だった。手術の内容は同じ箇所を切り開き、金属を取り出し、膿を除き内部を洗浄して元に戻すというもの。82才の高齢にとっては、わずか2ヶ月半後のリスクを伴う再手術であり、体への負担はかなり大きなものだった。予定時間は2時間だった。が、その頃を過ぎても連絡がない。羽田空港に着いて山梨までの帰路の途中、ずっと祈り続けた。1時間が過ぎ、2時間が過ぎた。妹も同じ気持ちだっただろう。彼女がしびれを切らし病院に電話してみると「まだ手術中です」との返事だったとのこと。「長引いている…」と思うと気が気でなかった。そうして私が暮らす上野原駅へ到着し、迎えに来てくれた友達に再会した直後に「無事終わったとの連絡あり」と妹からメールが入り、その場で地面にへたり込んでしまった。「あぁよかった…..。」
思えば、出発の時、妹が余市から小樽駅まで送ってくれた際、前を走っていた車のナンバーが829で、2年前に母が脳卒中で倒れて入院中に急死した父の誕生日であり、母が骨折した日だった「サインかな?」と妹と話しながら駅に到着。駅のホームで千歳空港行きの電車を待っていた時、外は雪が降っていて、乗客は電車が来るまで構内で待っていたが、3人だけは外にいた。それは私と若いカップルで、その彼女の方が話しかけてきた。聞くと2人は栃木から観光にやってきていて、彼女は大学3年生で彼は社会人1年生だという。電車がやってきて自然に隣の席に座り話を続けていると、彼女の名前は「はるな」だという。「えっ!」私を上野原駅で迎えてくれた友達の1人が「はるな」で彼女は今月入籍することになり、婚姻届の証人に私のサインを欲しくて、はるばる愛媛からやってきていたのだ。そして彼の職業を聞くとなんと「整形外科のリハビリテーション」だと言うではないか。「なんというシンクロ!」私は可笑しくて吹き出しそうになったが、つまりはそういうことだったのだろう。「すべては大丈夫!」だと。再びゼロからのスタートになったが、ここから光を目指す道が開かれるのだと信じていきたい。決して希望を失わずに。母が痛みを持って教えてくれていること。反面教師という意味でも、やはり彼女は私の先生なのだとそう思った。
ありがとうお母さん。これからもあなたを思って祈り続けます。